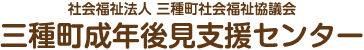🌸 2025年、明けましておめでとうございます!
今年はどんな1年になるのでしょうね。災害や争いの少ない穏やかな年になることを願います。
みなさんは、2024年をふりかえって、どんな1年だったでしょうか?
三種町成年後見支援センターは、2023年(令和5年度)開催の市民後見人養成講座を修了した10名のうち5名が支援員(生活支援員、後見支援員)として活動してくださり、目下、経験を積んでいるところです。
支援員のみなさんが、やりがいを感じ、自分なりの楽しみ(利用者との交流が楽しい、仲間と学べて嬉しい、など)を見つけながら活躍できるよう、バックアップしていきたいと思います。
- 最近あったエピソード紹介(一部加工しています)
支援員として活動をスタートしたAさん。担当した利用者Bさん宅に月1回、訪問しています。
Bさんは、アルツハイマー型認知症の診断がついていますが、毎日新聞を読み、話題が豊富です。
記憶の保持が難しいので金銭管理には支援を要する状態です。
AさんとBさんは、会話が弾み、Bさんは自分の家族のこともいろいろ話してくれたそうです。「孫が毎日会いに来るよ」など。
しかし、活動を終え、社協職員にBさんから聞いた話をすると、どうやら事実と異なるようです。孫は毎日会いに来ていません。
Aさん「自分の思っていた認知症のイメージと、流暢に話すBさんの状態が合わないように思う。接し方を変えた方が良いのかな?」と思ったようです。
Bさんのように、日常的な会話やコミュニケーションに一見問題がないように見える方でも、認知症の診断がついている場合があります。
認知症の診断は、脳の画像診断や、質問式のアセスメントツール(改訂 長谷川式簡易知能評価スケールなど)、観察式のアセスメントツール(本人の観察、家族や介護者からの情報による評価)などを用いて、医師が総合的に判断します。
Bさんのように会話はスムーズにできても、通帳の紛失を繰り返したり、事実と異なることを事実と認識したりしている場合もあるのです。
もしもAさんの中で、「認知症=(イコール)意思疎通が困難」というイメージだとしたら、Bさんの状態は、ちょっと違うかもしれませんね。
でも、自分の話にきちんと耳を傾け、否定せず、素直に感情表現をされたAさんの姿勢は、Bさんにとって嬉しかったのではないかと思います。
社協職員としては、「今までのような関わり方でいいと思いますよ。今後、認知症について一緒に学んでいきましょう。」と伝えました。
これから認知症について学び、認知症に対するイメージが変わったり、知識を備えたうえで、今のように関われたら、支援員として、もっといい活動になるのではないかな、と思ったエピソードでした。
そんなこともきっかけとなり、次回の権利擁護カフェ(支援員の研修会)のテーマは、
「学ぼう・語ろう・認知症」です。
長くなったので、続きはまた次回にします。